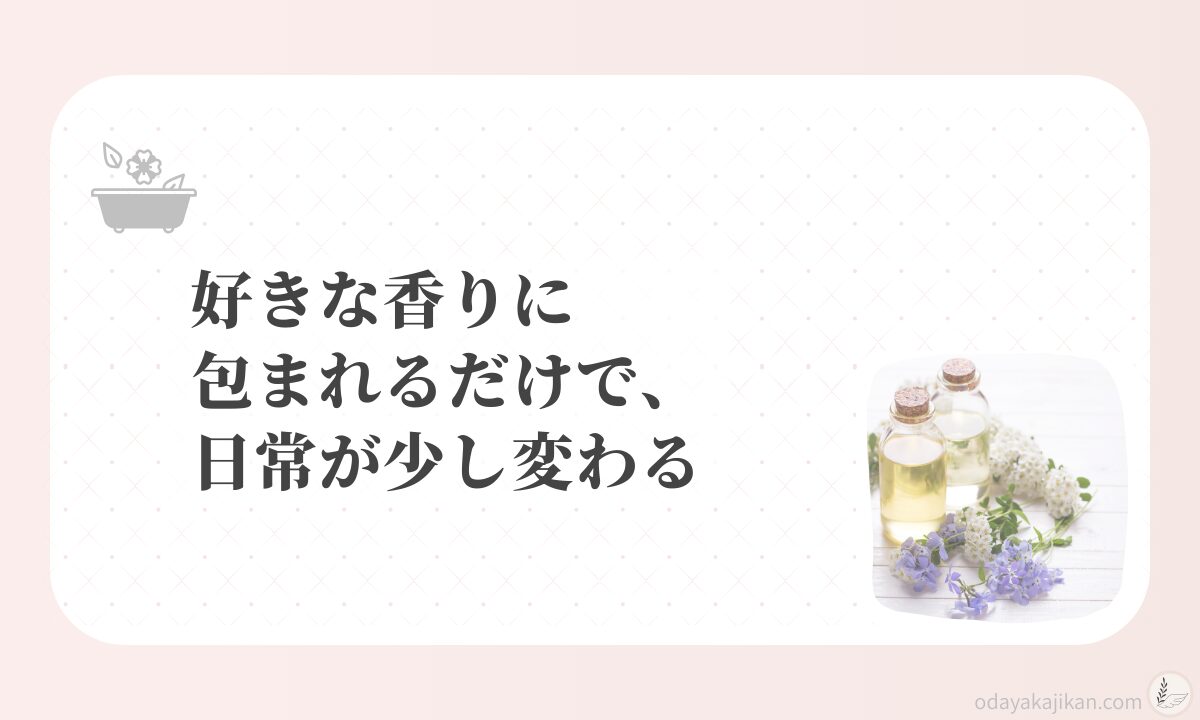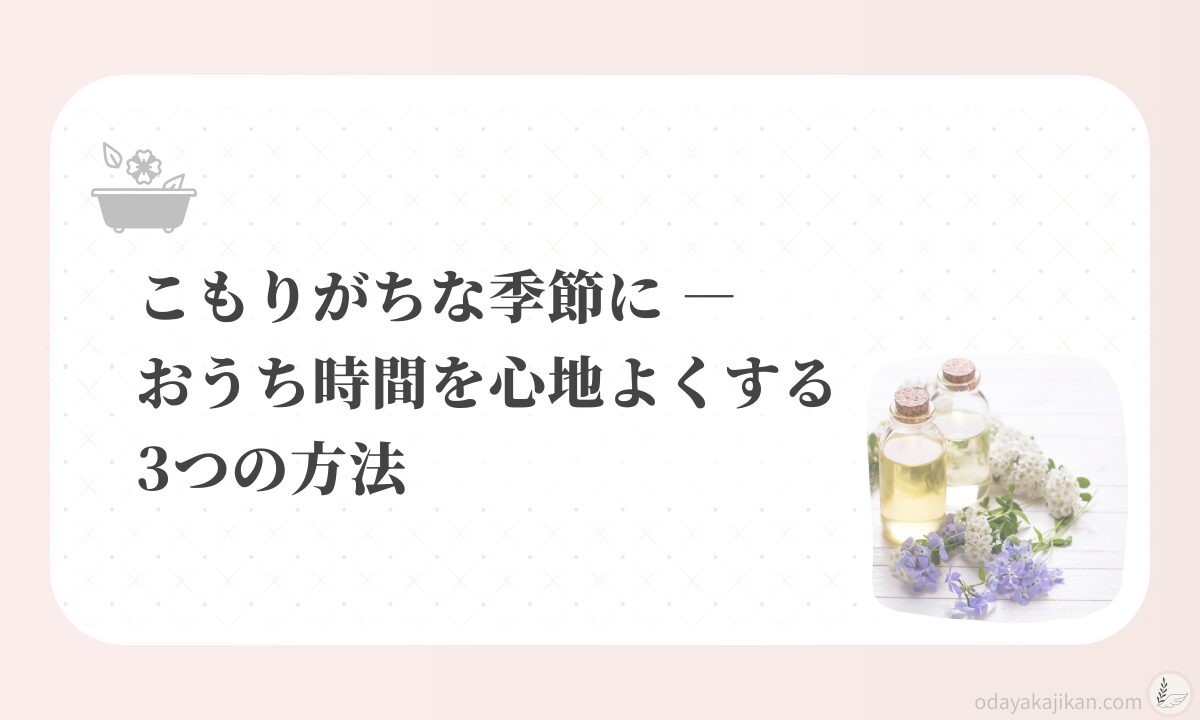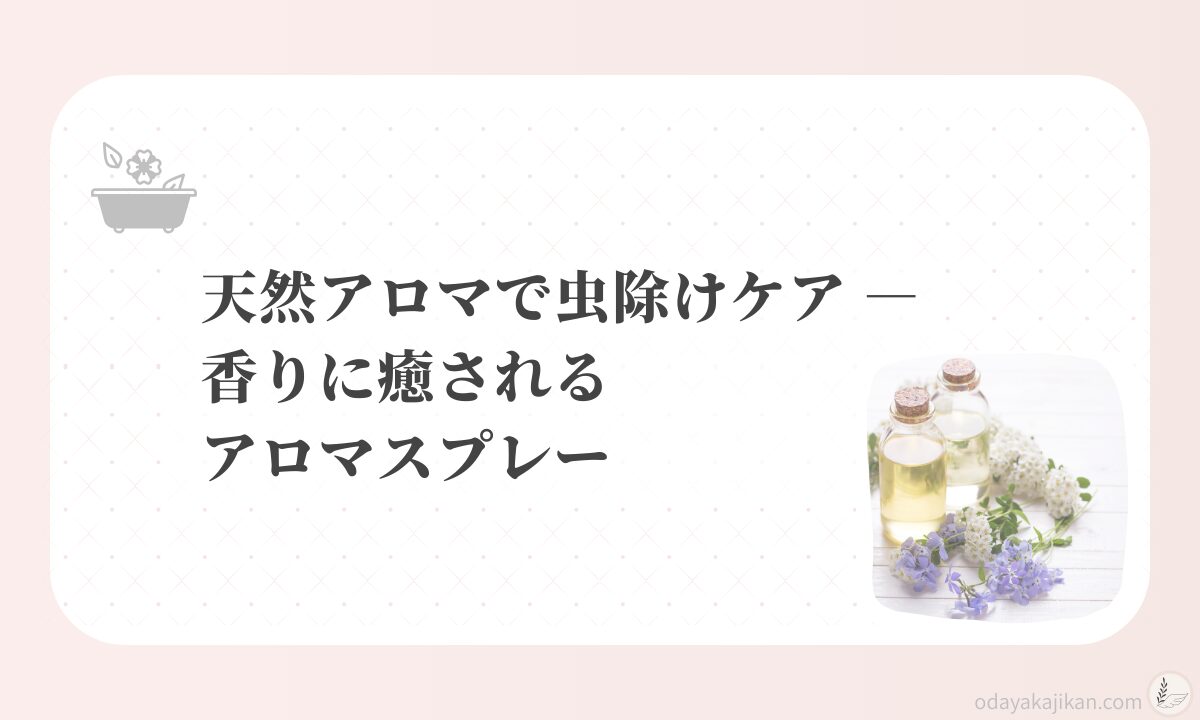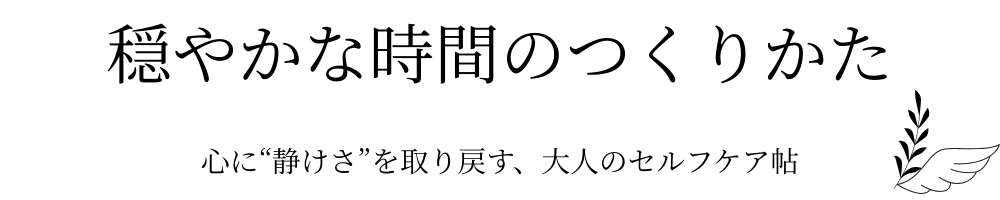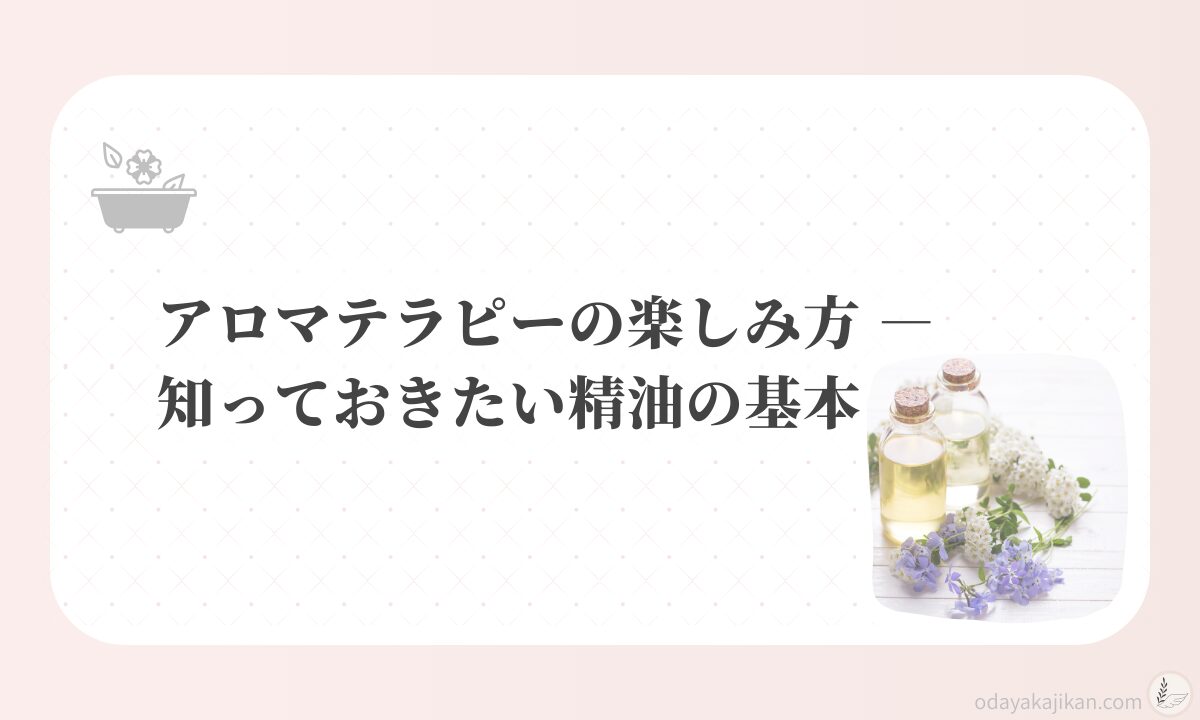植物の香りで穏やかな時間を作る、アロマテラピーの始め方
忙しい毎日の中で「ホッと一息つけるひととき」を作りたい…そんな風に感じることはありませんか?
植物の香りには、心を落ち着かせる不思議な力があります。
お気に入りの香りに包まれていると、自然と肩の力が抜けて、穏やかな気持ちになれるものです。
「アロマテラピーに興味はあるけれど、精油って難しそう」
「何から始めたらいいかわからない」
このような声をよく耳にします。
確かに精油は植物から抽出された濃縮成分なので、正しい知識を持って使うことが大切です。
今回は、アロマテラピー初心者の方が安心して香りのある暮らしを始められるよう、精油の基礎知識から安全な楽しみ方まで、わかりやすく解説していきます。
植物の香りを味方につけて、毎日に「穏やかなひととき」を取り入れてみませんか?
アロマテラピーってなに?

植物の香りで心と暮らしを整える自然療法
アロマテラピーとは、植物から抽出した香り成分(精油)を利用して、心身のバランスを整える自然療法のことです。
医療行為とは異なり、日常生活の中で気軽に取り入れられるセルフケアの一環として親しまれている存在です。
香りを楽しむことで気分転換になったり、リラックスタイムがより充実したりと、暮らしの質を高めてくれる存在と考えるとよいでしょう。
公益社団法人 日本アロマ環境協会(AEAJ)では、以下のように定義されています。
アロマテラピーは、植物から抽出した香り成分である「精油(エッセンシャルオイル)」を使って、美と健康に役立てていく自然療法です。
アロマテラピーの目的
・心と身体のリラックスやリフレッシュを促す
・心と身体の健康を保ち、豊かな毎日を過ごす
・心と身体のバランスを整え、本来の美しさを引き出す
「アロマテラピー」と「アロマセラピー」どっちが正しい?
時々「アロマテラピー」と「アロマセラピー」、どちらが正しいのか疑問に思われる方がいらっしゃいます。
実はどちらも同じ意味で、表記の違いは言語の違いによるものです。
「アロマテラピー」はフランス語由来で、「アロマセラピー」は英語由来の表記。
日本では「アロマテラピー」という表記が一般的に使われているため、当ブログでも「アロマテラピー」と統一してご紹介しています。
昔からあった、香りを暮らしに活かす知恵
古代から続く香りの歴史
植物の香りを暮らしに活用する知恵は、実は何千年も前から存在しています。
古代エジプトでは神々への捧げものとして薫香(くんこう)が焚かれ、中世ヨーロッパでは薬草が人々の健康維持に役立てられてきました。
現代のアロマテラピーは、20世紀初頭にフランスの化学者ルネ・モーリス・ガットフォセが精油の可能性に注目したことから始まったとされています。
私たちが今楽しんでいるアロマテラピーも、こうした長い歴史の延長線上にあるのですね。
精油選びで失敗しないために

「精油」と「アロマオイル」は別もの?
天然100%かどうかが大きな違い
店頭で香りのオイルを見ていると「精油(エッセンシャルオイル)」と「アロマオイル」という表記を目にしますが、この2つには重要な違いがあります。
精油(エッセンシャルオイル)は、植物から抽出された天然100%の香り成分です。
一方、アロマオイルという名称で販売されているものの中には、合成香料や他のオイルが混ぜられている場合もあります。
アロマテラピーを楽しむ際は、「精油」または「エッセンシャルオイル」と表記されている天然100%のものを選ぶのがおすすめです。
パッケージに学名や原産国、抽出部位が明記されているかどうかも、良質な精油を見分けるポイントになります。
精油はどうやってできる?
大量の植物からわずかな精油が生まれる
精油は主に水蒸気蒸留法や圧搾法などの方法で植物から抽出されます。
例えば、ラベンダー精油1滴を作るのに約100本のラベンダーが必要と言われているほど、非常に濃縮度の高いものなんです。
この高い濃縮度こそが精油の特徴であり、同時に取り扱いに注意が必要な理由でもあります。
少量でもしっかりと香りを感じられる一方で、刺激が強すぎる場合があるため、適切な方法で使用することが大切です。
初心者さんによくある疑問
初心者さんがよく疑問に思うことをまとめてみました。
- 精油は飲めるの?
-
日本では精油の飲用は推奨されていません。
海外では精油を内服する場合もありますが、日本では精油の飲用やうがいでの使用は推奨されていません。
高濃度の成分が健康への悪影響を及ぼすリスクがあるためです。 - 何滴くらい使えばいいの?
-
芳香浴なら1~3滴から始めてみましょう。
初めて使う精油は、まず少量から試してみるのがおすすめです。
6畳程度のお部屋なら1~2滴でも十分香りを感じられます。
香りの強さは個人の好みもあるので、少しずつ量を調整してください。 - 開封後どのくらい持つの?
-
柑橘系は半年~1年、その他は1~2年が目安です。
精油は天然成分のため、開封後は徐々に品質が変化します。
特に柑橘系の精油は酸化しやすいため、開封後は半年から1年以内に使い切るのが理想的。
その他の精油は1~2年程度が目安となります。
初心者におすすめの精油3選
(ラベンダー・スイートオレンジ・ティートゥリー)
迷ったらこの3つ
アロマテラピーを始めるにあたって「どの精油を選べばいいかわからない」という方も多いでしょう。
そんな時は、以下の3本から始めてみることをおすすめします。
ラベンダー:リラックスの定番
ラベンダーは「アロマテラピーの万能選手」とも呼ばれる、初心者さんに最もおすすめの精油です。
優しく穏やかな香りで、寝室での芳香浴やリネンスプレーなど、さまざまな場面で活用できます。

スイートオレンジ:明るく親しみやすい香り
柑橘系の中でも特に親しみやすいのがスイートオレンジです。
明るく温かみのある香りは、お部屋の空気を一変させてくれます。
朝のリフレッシュタイムにもぴったりですね。

ティートゥリー:すっきりとした清涼感
オーストラリア原産のティートゥリーは、クリアですっきりとした香りが特徴です。
お掃除用のスプレーに加えたり、玄関での芳香浴に使ったりと、生活のさまざまなシーンで活躍してくれます。

選ぶときのポイント
信頼できる品質の見極め方:精油を購入する際は、以下のポイントをチェックしてみてください
・価格があまりに安すぎないもの(天然100%の精油には相応のコストがかかるため)
・遮光瓶に入っているもの
・学名・原産国・抽出部位が明記されているもの
・信頼できるブランドから購入する
最初は専門店やアロマテラピー検定対応ブランドから購入すると安心です。
今日からできる!精油の楽しみ方4選

1. 香りを楽しむ「芳香浴」(一番簡単!)
アロマストーンでお手軽スタート
精油を始めて使う方には、アロマストーンが最もおすすめです。
電気も火も使わず、精油を数滴垂らすだけで香りを楽しめます。
デスクの上、ベッドサイド、玄関など、どこにでも置けるのも魅力的ですね。
ディフューザーで本格的な芳香浴
お部屋全体に香りを広げたい場合は、超音波ディフューザーやリードディフューザーがおすすめ。
水に精油を数滴垂らすだけで香りがお部屋に広がります。
身近なもので今すぐ試せる方法
「まずは香りを試してみたい」という時は、ティッシュに1滴垂らすだけでも十分楽しめます。
枕元に置いたり、デスクワーク中に近くに置いたりと、気軽に香りを感じられますよ。
2. オリジナルの「アロマスプレー」を作ってみる
手作りアロマスプレーは、思っているより簡単に作ることができます。
材料(50mL分)
- 無水エタノール:5mL
- 精製水:45mL
- 精油:10滴程度
- スプレーボトル(遮光性のあるもの)
作り方
- スプレーボトルに無水エタノールを入れる
- 精油を加えてよく混ぜる
- 精製水を加えて再度よく振る
- 使用前には毎回よく振ってから使用する
用途別アレンジ方法
ルームスプレー:来客前やお部屋の空気を変えたい時に便利です
リネンスプレー:枕やタオルにシュッとひと吹きするだけで香りを楽しめます
マスクスプレー:外出時も自分だけの香りで穏やかな気持ちで過ごせそうです
3. お風呂で贅沢な「アロマバス」
安全なアロマバスの楽しみ方
精油をお風呂で楽しむ際は、そのまま湯船に垂らすのではなく、必ず希釈してから使用しましょう。
精油は水に溶けにくく、原液のまま入浴すると肌への刺激となる場合があります。
- 天然塩大さじ1に精油1~3滴を混ぜてから湯船へ
- 植物オイル小さじ1に精油1~2滴を混ぜてから湯船へ
- はちみつ小さじ1に精油1~2滴を混ぜる方法も
入浴後のケアも大切
アロマバス後は、肌の状態を必ずチェックしてください。
赤みやかゆみが出た場合は、その精油の使用を控え、必要に応じて医師に相談しましょう。
精油を湯船に入れない方法
アロマバスとして湯船に入れなくても、以下の方法で入浴中に香りを楽しむことができます。
・洗面器やボウルを用意する
・好みの精油を1〜2滴入れる
・洗面器の中にシャワーで熱めのお湯をかける
シャワーで上がった湯気で香りを楽しむことができます。
肌の弱い方などはアロマバスにせず、このような方法がおすすめです。
4. 上級者向け「アロマトリートメント」
精油を肌に直接使用するトリートメントは、正しい知識と技術が必要な上級者向けの楽しみ方です。
精油をキャリアオイルで希釈して使用します。
キャリアオイルとは?
キャリアオイルは、精油を希釈するためのベースとなるオイル(植物油)です。
精油を肌に使用する際は、必ずキャリアオイルと混ぜて濃度を調整します。
- ホホバオイル:肌になじみやすく、酸化しにくい
- スイートアーモンドオイル:マイルドで敏感肌にも優しい
- グレープシードオイル:さらっとした使用感、べたつかない
- フェイシャル:0.5%以下(キャリアオイル10mLに精油1滴)
- ボディ:1%以下(キャリアオイル10mLに精油2滴)
濃度が濃すぎると肌トラブルの原因になるので、最初は薄めから試して肌の様子を見ながら使用してください。
公益社団法人 日本アロマ環境協会(AEAJ)でも「肌に精油を使用する際は低い濃度で試してから使う」ことが推奨されています。
精油を安全に使うための注意点とNG例

原液のまま肌に使用しない
精油は高濃度の植物成分が凝縮されているため、原液のまま肌につけると刺激となる場合があります。
原液のまま肌に使用することは避けてください。
芳香浴以外で精油を使用する際は、必ず適切に希釈してからご使用ください。
特に注意が必要な人・ペット
妊娠中・授乳中の方
妊娠中や授乳中は、普段より肌が敏感になったり、香りに敏感になったりする場合があります。
精油を使用する前に、医師や助産師に相談されることをおすすめします。
3歳未満の乳幼児
小さなお子様は大人より敏感で、精油の成分に強く反応する場合があります。
3歳未満のお子様がいるご家庭では、芳香浴も控えめにし、お子様の様子を注意深く観察してください。
ペットへの配慮
特に猫には危険とされる精油があります。
また、犬や他の小動物にも悪影響となる場合がありますので、精油の使用前に獣医師に相談するか、ペットのいない部屋での使用に留めることをおすすめします。
知っておきたい「光毒性」
柑橘系精油を使う時の注意点
光毒性とは、柑橘系精油に含まれる成分が紫外線と反応して、肌にシミや炎症を起こす現象のことです。
レモン、ベルガモット、グレープフルーツなどの精油を肌につけた後は、約12時間は直射日光を避けるようにしましょう。
夜のスキンケアとして使用するか、光毒性成分を除去した「FCF(フロクマリンフリー)」タイプの精油を選ぶのがおすすめです。
精油を長持ちさせる保管方法
正しい保管で品質を保つように心がけましょう。
・遮光瓶のまま保存(透明な瓶への移し替えはNG)
・冷暗所での保管(直射日光・高温多湿を避ける)
・開封後は空気に触れる時間を最小限に
・購入時に開封日をラベルに記入する習慣を
冷蔵庫での保管も可能ですが、使用する際は室温に戻してからお使いください。
原液は肌につけない
妊娠中・小さなお子さん・ペットには注意
柑橘系は光毒性に注意
「難しそう」と思ったら、まずはこれから

火も電気も使わない「アロマストーン」
アロマテラピーに興味はあるけれど「難しそう」、「何を揃えればいいかわからない」という方には、アロマストーンから始めることをおすすめします。
素焼きや石膏でできた小さなストーンに精油を数滴垂らすだけで、自然な香りを楽しめます。
火や電気を使わないため安全性が高く、お手入れも簡単。
価格も手頃で、初めてのアロマグッズとして最適です。
持ち歩ける「アロマサシェ」
アロマサシェは、小さな布袋に精油を1滴垂らして作る携帯用の香り袋です。
バッグに忍ばせておけば、外出先でも自分だけの香りでリラックスできます。
クローゼットや引き出しに入れて、衣類に仄かな香りをつけるのもおすすめの使い方です。
既製品のアロマグッズから始める
精油の扱いに不安がある方は、既製品のアロマグッズから始めてみるのも一つの方法です。
精油成分が入ったルームスプレーや入浴剤など、安全性を考慮して作られた製品が数多く販売されています。
既製品で香りのある暮らしに慣れてから、少しずつ手作りにチャレンジしてみてくださいね。
この記事の内容について
本記事の内容は、公益社団法人 日本アロマ環境協会(AEAJ)の定義とガイドラインに基づいて作成しています。
アロマテラピーは医療行為ではなく、心身の健康維持やリラクゼーションを目的とした自然療法の一つとしてご紹介しています。
持病がある方、妊娠中・授乳中の方、小さなお子様やペットと暮らしている方は、精油をご使用になる前に医師や専門家にご相談されることをおすすめします。
香りのある暮らしで、穏やかなひとときを
アロマテラピーは決して「特別なもの」ではありません。
正しい知識を身につければ、どなたでも安心して日常に取り入れられるセルフケアの方法です。
まずは好きな香りを見つけて、アロマストーンでの芳香浴など簡単な楽しみ方から始めてみてください。
慣れてきたら手作りスプレーやアロマバスなど、少しずつ楽しみ方の幅を広げていけばよいでしょう。
植物の香りには、忙しい毎日の中で私たちの心を穏やかにしてくれる力があります。
あなたも香りのある暮らしで、毎日に「穏やかなひととき」を取り入れてみませんか?
関連記事
▼「香り」に関する記事